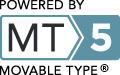利息制限法と過払い金の計算方法、取引の分断と再契約について
利息制限法には、利率の上限が定められています。本来、金銭消費貸借における利率は、公序良俗に反しない範囲で自由に定めることができるはずです(契約自由の原則)。しかし、経済的弱者である借主は、貸主に対して希望を通すことが難しく、貸主の言いなりの利率で契約してしまうこととなりがちです。これを防ぐため、あらかじめ利息制限法により利率の上限が定められているのです。同様の趣旨をもつ法律には、消費者契約法があります。消費者と事業者の間には情報力に格差があるため、一般的に不利な立場に置かれる消費者の利益保護を図る趣旨で2001年に施行されました。
利息制限法の上限金利を超えた契約が長期間継続すると、過払い金が発生していることがあります。長期間の取引により徐々に元本が減少し、元本が0となった後も支払いを継続することにより発生します。過払い金は、法律上不当利得となり、民法704条により返還請求ができます。
過払い訴訟においてしばしば争いとなるのは、取引の途中に完済をし、その後に際借り入れをした場合の計算方法です。いったん完済した際に発生した過払い金を、再借り入れ時の借り入れ金に充当計算するのかどうかが問題となります。
もし充当ができない場合には、貸付金の利率(多くは18%)と、民法704条により過払い金に発生する利息の利率(5%)に差があるため、過払い金の額が減少することになります。さらに、過払い金の時効は、最高裁平成21年1月22日により、取引終了時から10年で時効にかかるため、取引中断が10年以上前である場合には、過払い金が消滅時効にかかり、消滅してしまうことがありえます。
しかし、再借り入れ時の貸付金に充当ができれば、時効消滅することはありません。この点については、最高裁平成20年1月18日判例などで、充当の可否に関する基準が示されていますが、どのようなケースで充当が認められるかは、裁判所によっても判断にばらつきがあり、予測が立てにくい争点となっています。この、「完済後再借り入れをした場合の過払い金の充当」については、いくつかの最高裁判例があります。まず、同一の基本契約中で発生した過払い金は、その後の借入金に充当されると判示したのが、最高裁判所第一小法廷平成19年6月7日判決です。消費者金融などの契約は、弁済と貸付が繰り返され、その対応関係はないというのが一般的な取引です。弁済と貸付に対応関係がないというのは、弁済が過去の借入金の合計額全部に対する弁済となるという意味です。このような契約を締結して継続的に取引をしている場合、その契約内では、過払い金が発生した場合にもその後に発生した借入金に充当するという合意(これを、過払い金充当合意とよびます)があると考えてよいという判断をしたのです。
では、基本契約が二つある場合、つまり、一旦基本契約を解約して、再度基本契約を締結している場合は、前の契約で発生した過払い金を後の基本契約で発生した借入金に充当することはできないのでしょうか。この点について判断をした判例としては、最高裁判所第二小法廷平成20年1月18日判決があります。一部、引用します。
同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債務が存在せず,その後に,両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は,第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当されないと解するのが相当である(最高裁平成19年2月13日第三小法廷判決参照)。そして,第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さやこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間,第1の基本契約についての契約書の返還の有無,借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無,第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況,第2の基本契約が締結されるに至る経緯,第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には,上記合意が存在するものと解するのが相当である。
この最高裁判決でしめされた基準を具体的事例にあてはめて、今後は基本契約の異なる二つの取引の充当の可否が判断されることになります。